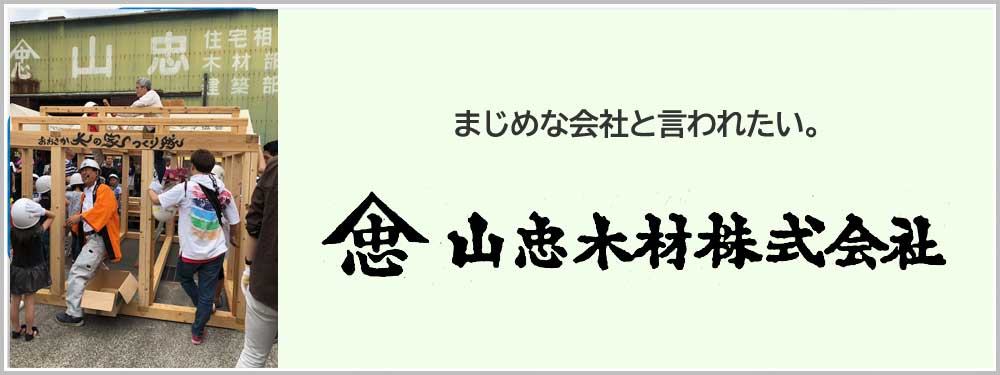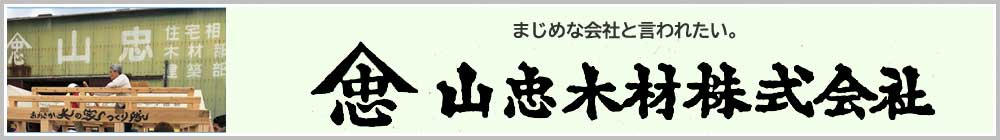血管の若さを保つ 酸化・糖化 食い止めて
糖質と脂質控える / 有酸素運動や入浴を
*血管は血液によって体の隅々に酸素や栄養を届け、老廃物や二酸化炭素を回収します。
*血管を若く健やかな状態に保つことが重要。
*体の老化を促進する重要な要因とされる酸化と糖化は、いずれも動脈硬化にも関係。
*紫外線や有害物質などの影響で活性酸素が過剰に作られ、体内のタンパク質や脂質と反応して細胞を酸化させます。
*体内のタンパク質と食事で摂取した糖質に由来する成分が結びつき、体温の熱が加わることで褐色に変性し劣化します。
*糖化が進むと最終的には老化促進物質のAGEs(終末糖化産物)が生成されます。
*血管の老化を防ぐには、血管を傷めない生活習慣を実践することが大切。
*糖質と脂質の取り過ぎに注意。
*糖質の取り過ぎは、食後に血糖値が急上昇する食後高血糖(血糖値スパイク)を招きます。
⇒アルデヒドと呼ばれる複数種の有害物質が急増。
*脂質の取り過ぎは血液中の脂肪酸の増加につながります。
⇒脂肪酸が酸化することでもアルデヒドが発生します。
*糖質を抑えるには、ごはんやパンなど主食の量を控え、1日3食のうち1食は玄米や雑穀などの全粒穀物に。
*脂質は摂取量を減らしつつ、青魚や植物油などに豊富なオメガ3脂肪酸など良質なものを意識。
*食べ方の工夫としては、食物繊維が豊富な野菜から食べます。
*高血圧の予防には、塩分を控え、十分な睡眠をとることも大切。
*喫煙習慣のある人は禁煙も。
*息が少し弾んでも笑顔で会話ができる程度に早歩きする「ニコニコ歩き」を1日30分、週3日以上習慣に。
*有酸素運動で血管に適度な振動が伝わると、血管の内側の内皮細胞で血管を拡張する作用のある一酸化窒素(NO)が産生され、血管をしなやかにします。
*平均年齢65歳の健康な人たちでは、週5日以上、41度程度の熱めのお湯で10分程度の浴槽入浴をする人は、そうでない人に比べて血管が若く、心臓も健康なことを確認。
(2025年8月2日 日本経済新聞記事より抜粋・引用)
胃食道逆流症 胃酸逆流し胸やけや咳
肥満や姿勢も影響 / 再発率も高く
*胃と食道の間には「下部食道括約筋かつやくきん」と呼ばれる筋肉があり、弁のような役割を果たして胃内容物の逆流を防ぎます。
*括約筋の機能が加齢や食生活などを理由に低下すると、胃酸が食道へ逆流しやすくなります。
*胃の動きが悪化して胃内容物が停滞したり、肥満や妊娠などで腹圧が上昇したりすることも逆流を助長します。
*逆流した胃酸は通常、唾液や蠕動ぜんどう運動によって胃に押し戻されますが、唾液分泌や食道運動が低下すると胃酸が長時間食道粘膜にとどまって炎症を起こしやすくなります。
*胸やけなどの典型的な症状は、食後や起床時などに起こりやすくなります。
*喉の違和感や咳、声がれなどが出ることもあります。
*治療の基本は薬物療法と生活習慣の改善。
*過食や脂肪分の多い食事は、胃内圧を上昇させたり胃の排出を遅らせたりして逆流を助長します。
*肥満は腹圧を高めるため、胃食道逆流症の主要なリスク因子。
*アルコールや喫煙は括約筋の弛緩しかんにつながります。
*消化機能の低下を招くストレスや不規則な生活も要注意。
*上体をやや起こし頭を高くして眠ることで、重力の助けにより胃酸の逆流を防止。
*左側を下にした寝姿勢(左側臥そくが位い)だと逆流が起こりにくいと考えられています。
*胃食道逆流症は再発率が非常に高く、1年以内に約60~80%が再発。
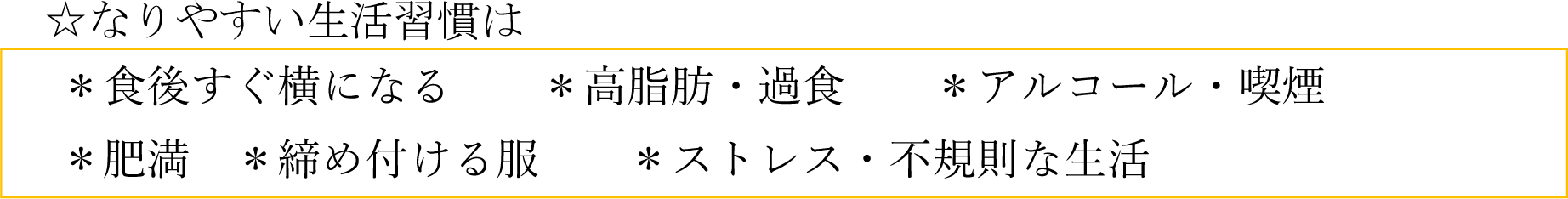
(2025年8月9日 日本経済新聞記事より抜粋・引用)
発酵性食物繊維 腸内環境よく 食事から
伝統の日本食に多く / 自分に合うか確認
*腸内環境にとっては大腸まで食物繊維が届き、腸内細菌によってよく「発酵」するかが重要。
*「発酵」:食物繊維が大腸まで到達し、ビフィズス菌や乳酸菌といった腸内細菌、いわゆる「善玉菌」のエサとなってエネルギーを作り出すプロセス。
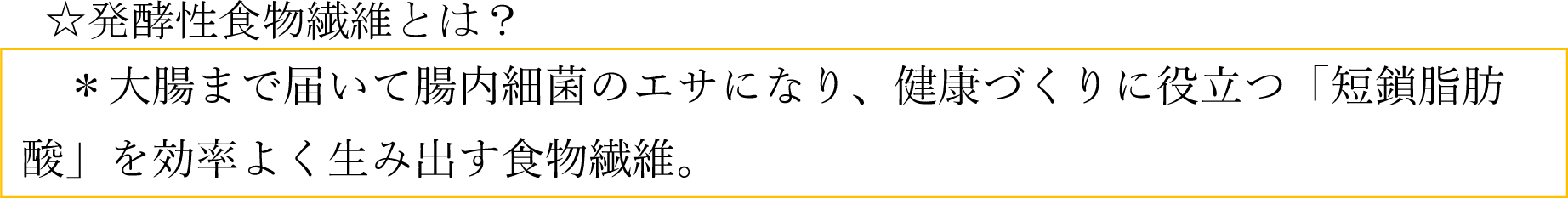
*伝統的な日本食には、多種多様な発酵性食物繊維が含まれています。
*ビフィズス菌は乳幼児期をピークに減り続けるため、中高年以上ではビフィズス菌入りのヨーグルトなどで意識的に体内に取り入れることが望ましくなります。
*それまであまり食べていなかった発酵性食物繊維を多く含む食材を摂取するとき、体調や便通の変化、アレルギーの有無に注意。
*自分に合った摂取パターンをみつけることが大切。
(2025年8月16日 日本経済新聞記事より抜粋・引用)
質の高い休養 「戦略的投資」
*戦略的に休養を取ることは単に疲れたから休むのでなく、睡眠やホルモン、自律神経を意識的に調整することにあります。
●睡眠の戦略化
*睡眠は1日7時間程度を確保。
*就寝前2時間は刺激が強いスマートフォンなどからのブルーライトを避けます。
*寝室の温度を夏場は25~28度に保てば、深い眠り(ノンレム睡眠)につながります。
*特に最初の3時間に訪れる不快睡眠段階で成長ホルモンが分泌され、細胞の修復と記憶の定着が行われます。
●ホルモンバランスの最適化
*適度な運動と良質な睡眠は、男性ホルモンの一種のテストステロンの分泌を促します。
*週3回、40~60分程度の有酸素運動を心がけます。
●自律神経の調整
*意識的にリラックスして副交感神経を優位に。
*瞑想や深呼吸はストレスホルモンのコルチゾールを低下させ、心拍変動を改善。
*就寝2~3時間前の入浴は体温調節を通じて自律神経を整えます。
(2025年8月16日 日本経済新聞記事より抜粋・引用)
長引く鼻づまり 副鼻腔の炎症で不快感
負担軽い治療登場 / 新しい薬や手術法
*風邪を引いた後などに、ウイルスなどが入り込み炎症を起こすと急性副鼻腔炎に。
*黄色くネバネバした鼻水が特徴。
*細菌などによる炎症が起こり3か月以上続くと慢性副鼻腔炎と診断されます。
*内部に膿が溜まり、頬や額などに痛みや「重だるい」不快感のことも。
*「好酸球性副鼻腔炎」:炎症にアレルギーが関与した副鼻腔炎。
*再発しやすい厄介な病気で、国が難病に指定。
*薬物療法は、マクロライド系の抗生物質を少量、長期間投与することで症状を抑える治療が中心。
*手術治療は、鼻に細い内視鏡と鉗子かんしやメスなどを挿入する内視鏡下鼻内副鼻腔手術。
*鼻腔粘膜を刺激する喫煙は止め、鼻づまりを悪化させる飲酒は控えめに。
*鼻水をすする習慣をやめます。
*本来は体外に排出すべき病原体や分泌物などを逆流させてしまいます。
*鼻をかむときは、左右交互にやさしくします。
*鼻水がなかなか排泄できないときは「鼻うがい」がお勧め。
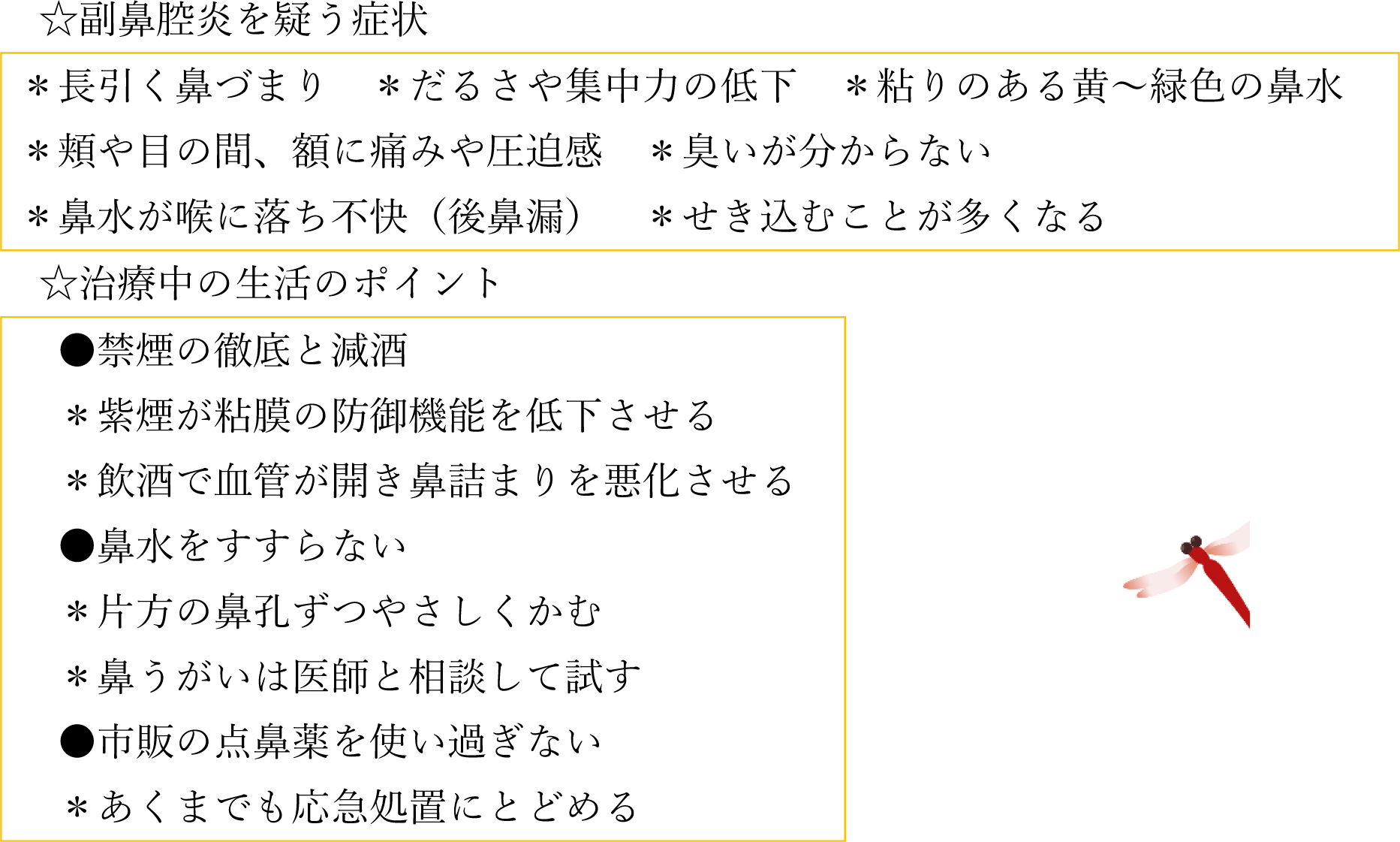
(2025年8月23日 日本経済新聞記事より抜粋・引用)
酷暑疲れと膀胱ぼうこう炎 冷房と水分不足に注意
排尿を我慢しない / 原因、細菌以外も
*膀胱炎の多くは、大腸菌などの細菌が尿道から膀胱内に侵入し増殖することが原因。
*体の構造的に尿道が短く、入り口が膣や肛門に近い女性は、男性より罹患率が高く。
*汗をかいて尿量が減りがちな夏は、膀胱内に濃い尿が長くたまり、細菌が増殖しやすい環境になります。
*過度の冷房による冷えも免疫力を低下させます。
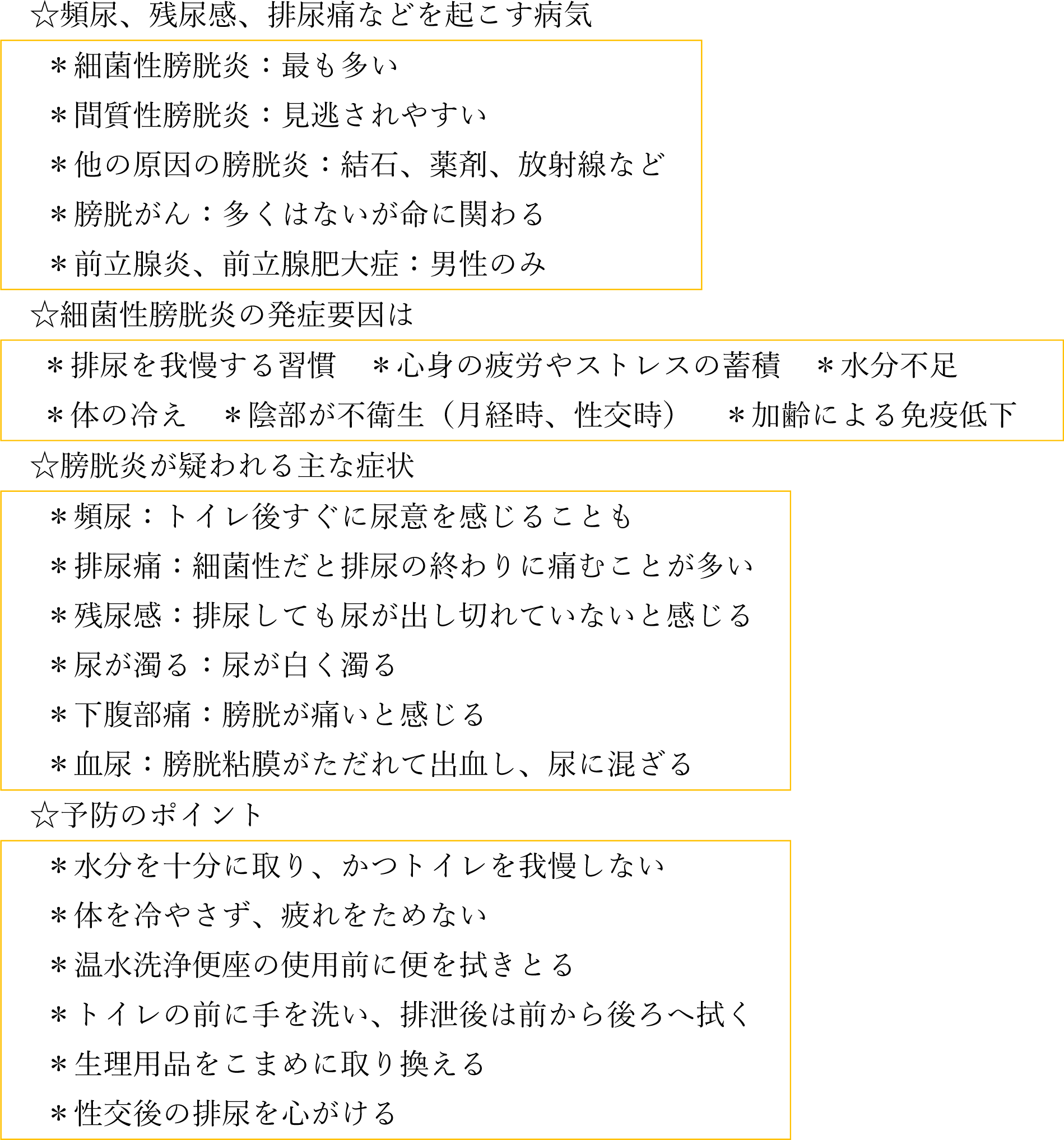
(2025年8月30日 日本経済新聞記事より抜粋・引用)
そうだ、銭湯へ行こう! 親子連れちょっと旅
大正区 大正湯
ここへ行くときは、いつものように帰りにたこ焼き{や~まん}に立ち寄るのが定番となりました。カウンターの隣で一人飲みしていたお兄ちゃんと加熱式タバコ談義をしました。
(2025.8.3)
大正区 いとうぴあ
数えてみると、先月から4週続けての大正区銭湯となりました。最近なかなか「遠征」をしてくれなくなりました。 “たろう”の体重が1年前の60㎏から71㎏になったのが要因かも。帰りは久しぶりの「お好み焼き ミサ」でした。
(2025.7.20)
浪速区 ヘルシー温泉桜川
この日の予定は「ヘルシー温泉タテバ」でした。
家から南泉尾の交差点で信号を待っていると、「大阪駅前」行のバスが通り過ぎてしまいました。時刻に合わせたつもりが間に合いませんでした。
次にバス停へやってきたのは「なんば」行でしたので、桜川でバスを降りて目的地へ向かいました。暑い盛りで日傘と陰に助けられて「ヘルシー温泉桜川」の横まで来ると、このお風呂屋さんに入ることで双方合意しました。
帰りは「松屋」でした。
(2025.8.17)
西成区 旭温泉
「中開き1丁目」のバス停で降りて、極力日陰を選んで南に歩きました。鶴見橋商店街のアーケードを横切りしばらくすると右側に銭湯が見え、“たろう”の同意を得て中に入りました。
下足箱から番台への引戸までの間が薄暗くて少し不気味な感じでしたが、脱衣場は広くて明るかったです。
この日の本当の目的地は以前にも行ったことのある「都温泉」でした。旭温泉とは一筋か二筋の道違いだったと思います。思いがけず初訪問の銭湯に行けてよかったです。過去の“たろう”だと、道すがら目指すお風呂屋さんとは異なる銭湯があっても見向きもしませんでした。少し融通が利くようになったようです。
帰りは商店街内の中華料理店に立ち寄りました。予定では久しぶりに商店街を最後まで歩いて渡し船で帰るルートでしたが、暑いので再びバスを使いました。
(2025.8.24)
大正区 こうわの湯
家から歩いて10分あまりの所をこの日もバスで行きました。
最寄りのバス停に到着する路線は大体1時間に1本なので、今回は予め時刻表を検索してから出発しました。
晴天の日の露天風呂は外気が気持ちよいです。ただ、いつものことですが、施設に入ってから出るまでの滞在時間は30~40分ほどです。
この日は食事は「すき家」だったので、予算内で済みました。
(2025.8.31)